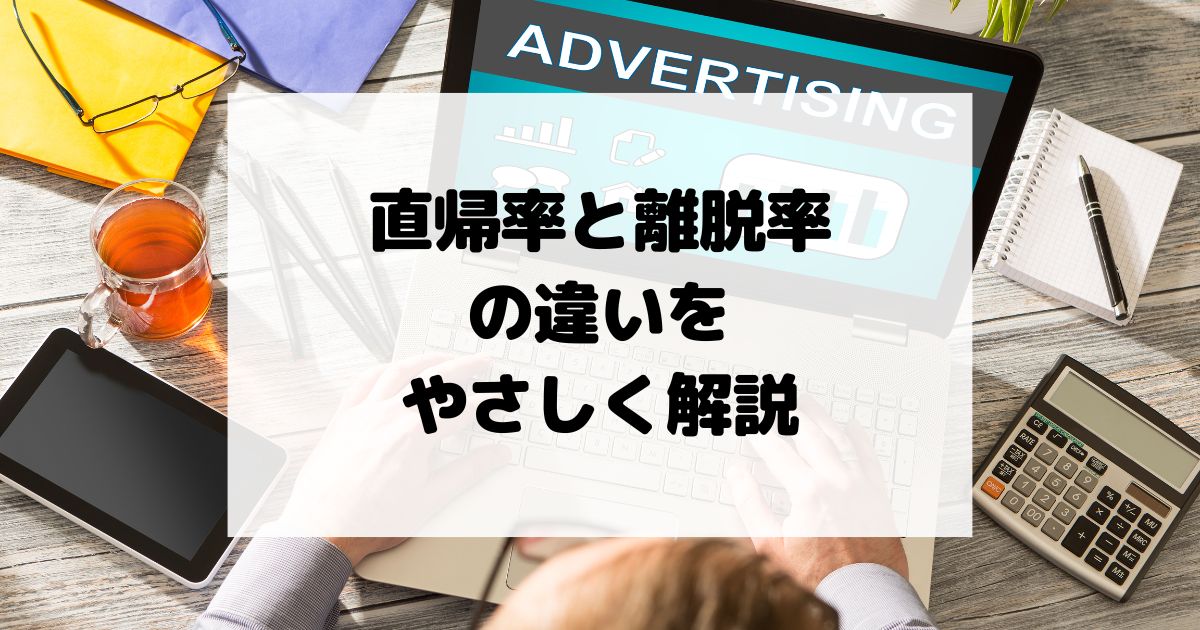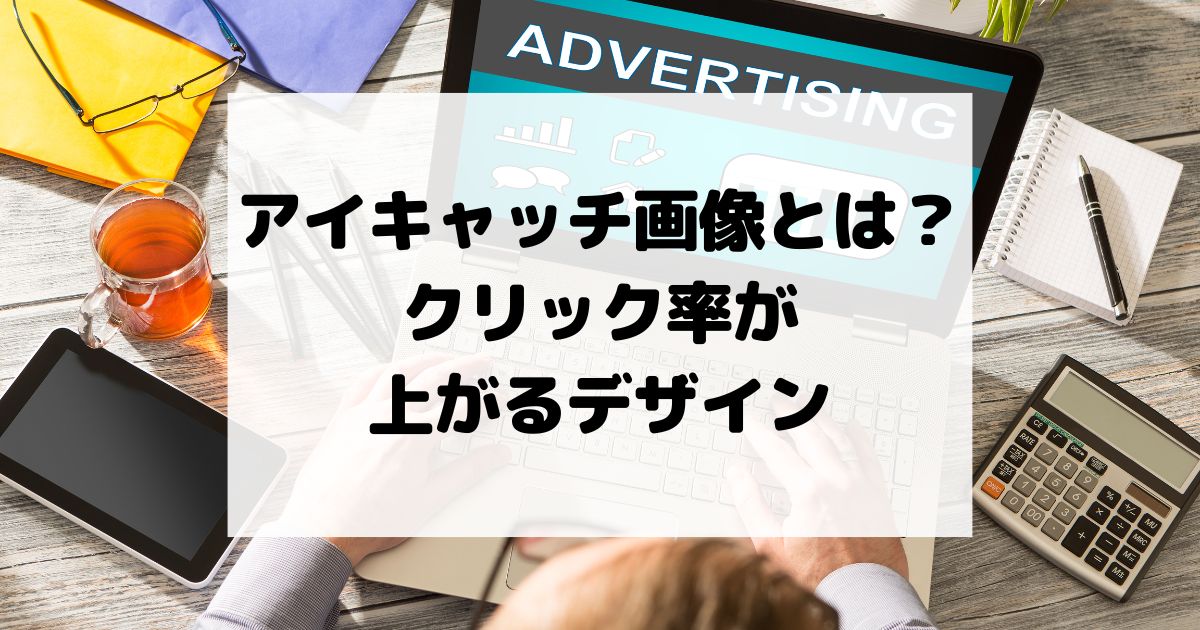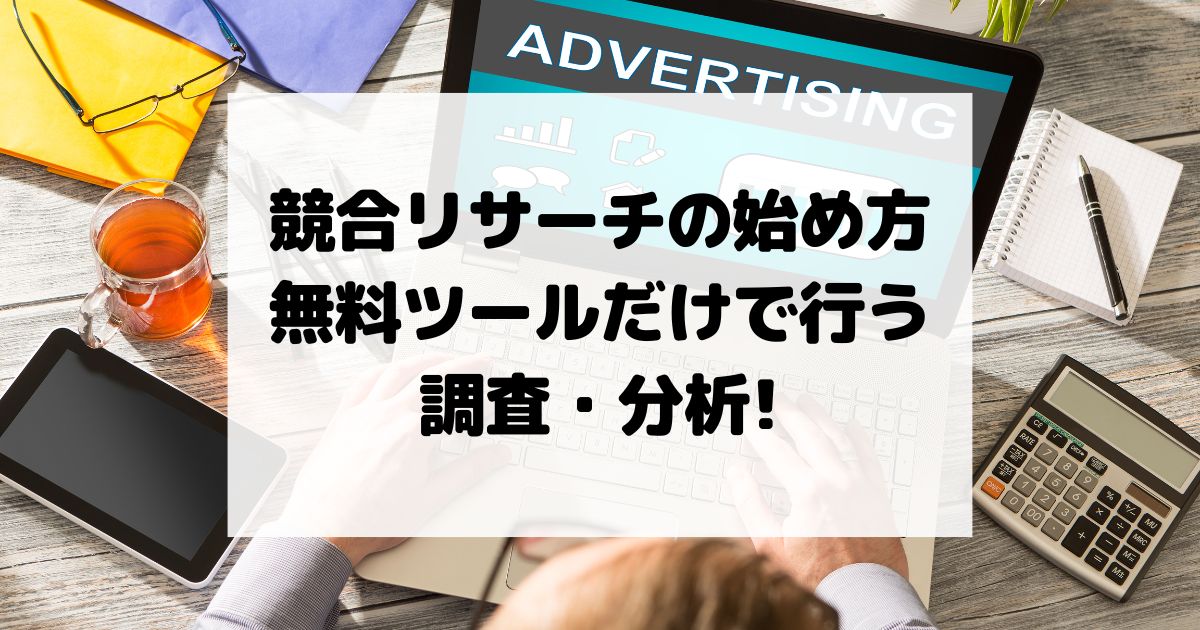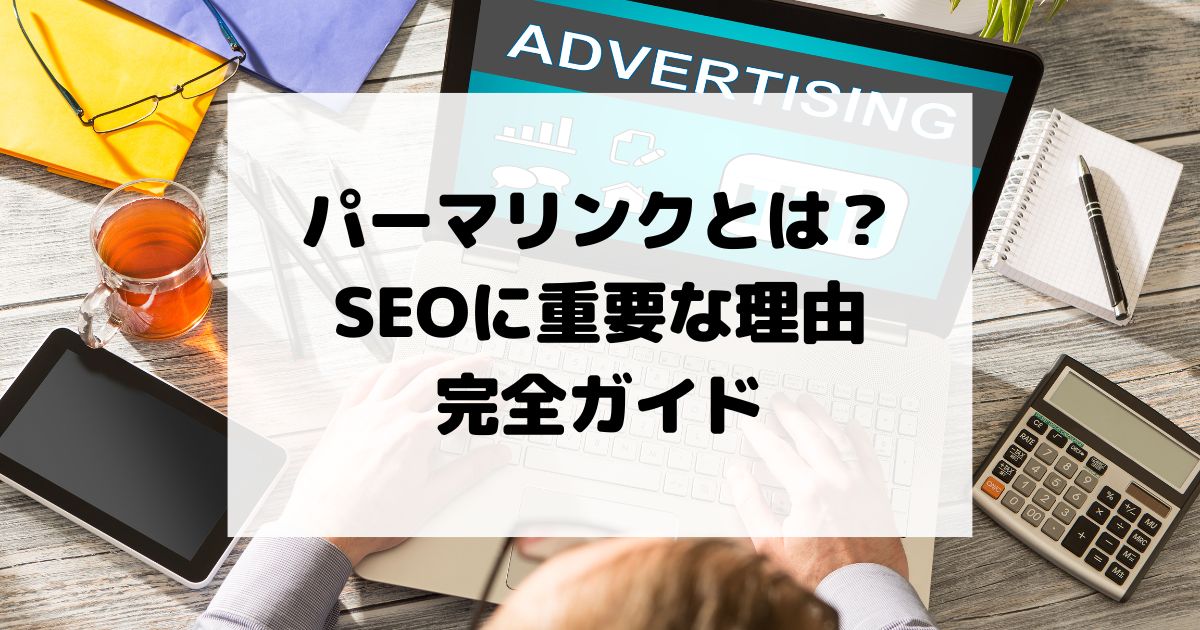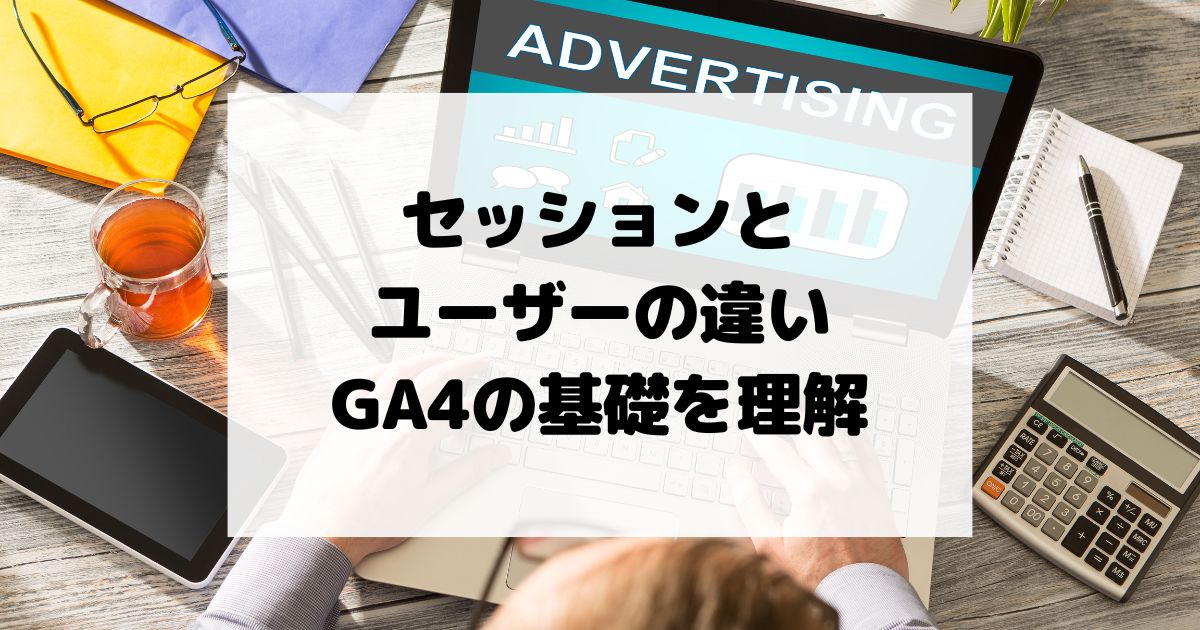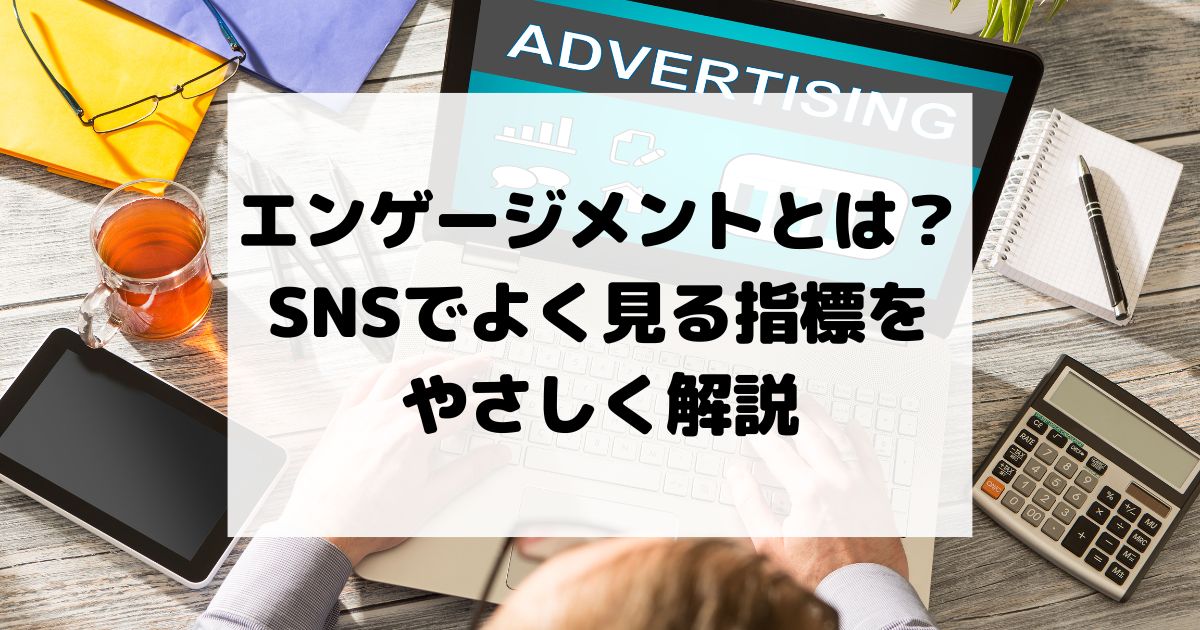ブランド認知広告と獲得広告の最適バランス|ファネル別KPI設計と予算配分の考え方
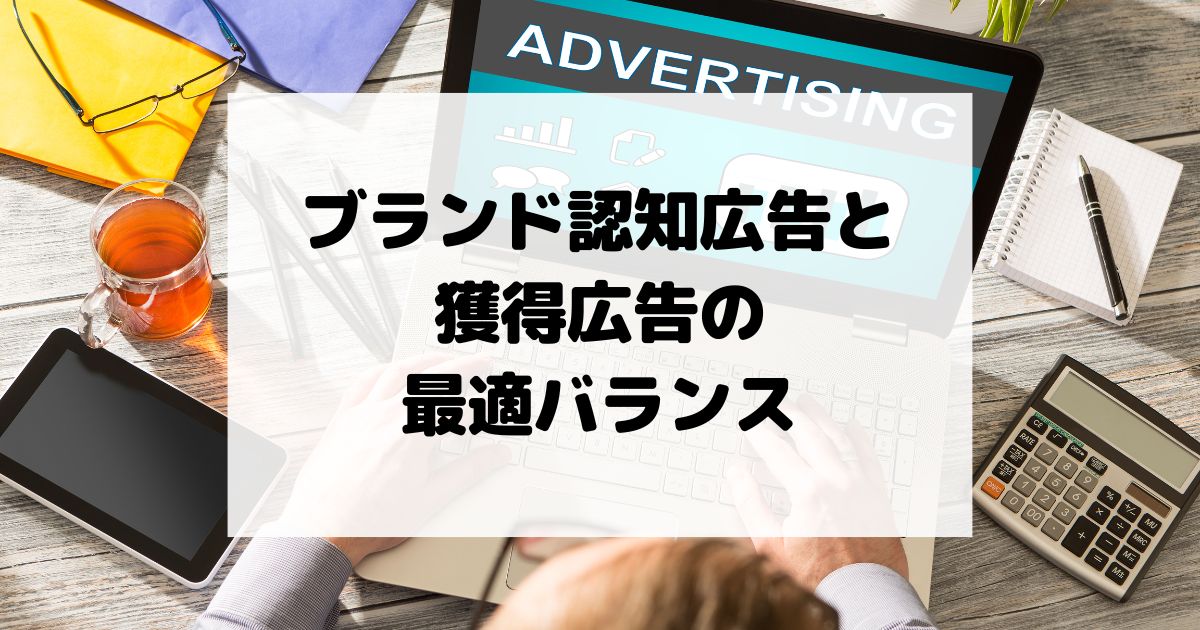
ブランド認知と獲得、どちらを優先すべきか?広告施策を成功させるには、ファネル別の役割とKPI、予算配分の設計が不可欠です。
ブランド認知広告と獲得広告の違いとは?
まず最初に、それぞれの広告が担う役割を明確にしておきましょう。
ブランド認知広告とは
- 目的:自社ブランドや商品を知ってもらうこと
- ターゲット:潜在層(まだ課題に気づいていない or 比較検討前)
- 配信面:YouTube、X(旧Twitter)、Meta、ディスプレイ広告など
- 成果指標:リーチ数、広告想起、動画再生率、ブランドリフトなど
獲得広告とは
- 目的:問い合わせ、購入、資料請求などの直接的なCV獲得
- ターゲット:顕在層(比較検討段階 or 今すぐ客)
- 配信面:Google検索広告、リマーケティング、SNSコンバージョン広告など
- 成果指標:CV数、CVR、CPA、ROAS
「認知だけ」「獲得だけ」の施策では成果は頭打ちに
広告運用では「獲得効率」ばかりを追いがちですが、認知の土台がなければ獲得の母数が増えません。
たとえば…
- 認知が弱い:検索ボリュームが少ない、指名検索が生まれない、広告を見ても知らないからクリックされない
- 獲得だけ:CVは取れるが、スケーラビリティに欠けて中長期の成長が止まる
逆に、認知施策だけを続けても、ビジネス成果には結びつかず「広告費が無駄」と感じられてしまうケースも。
よって、重要なのは
👉 ファネル構造に合わせて「認知」と「獲得」を戦略的に組み合わせることです。
ファネル別に見る広告の役割とKPI設計
マーケティングファネル(顧客の心理段階)に応じて、広告の目的・KPI・クリエイティブ内容を切り分けることで、施策の精度が高まります。
| ファネル | 目的 | 主な広告手法 | KPI |
|---|---|---|---|
| 認知 | 知ってもらう | YouTube広告、Meta動画、X広告 | リーチ数、再生率、CTR |
| 興味・関心 | 検討に入る | ディスプレイ、SNS静止画広告など | ページ滞在時間、クリック率 |
| 比較・検討 | 選ばれる | Google検索広告、リターゲティング | CVR、LP離脱率 |
| 行動(CV) | 問い合わせ等 | 検索リマーケ、コンバージョン広告 | CV数、CPA、ROAS |
このように段階ごとに広告設計を分けることで、KPIがブレず、判断と改善がしやすくなります。
ブランド認知広告と獲得広告の予算配分はどうすべきか?
結論から言うと、現時点のビジネスフェーズ・広告目的・商品単価・業種特性によって適切なバランスは異なります。
以下はあくまで一例ですが、参考になる配分パターンです。
【スタートアップ・新サービス立ち上げ時】
- ブランド認知:60〜70%
- 獲得広告:30〜40%
👉 まずは知ってもらうことに注力し、指名検索や流入を増やす土台づくり
【認知がある程度進んできたフェーズ】
- ブランド認知:30〜40%
- 獲得広告:60〜70%
👉 既に接点のある層に効率よくCVを促進し、CPAを最適化する
【中長期でスケールを目指すタイミング】
- ブランド認知:40〜50%
- 獲得広告:50〜60%
👉 常に新規を取り込みながら、安定した獲得を両立するバランス設計
広告配信の中で**ファネルの上から下へ「熱量を移していく導線設計」**が重要になります。
よくある失敗:KPIが“混在”している
「ブランド認知広告を出しているのにCVが取れない」
「獲得広告を回しているのにROASが悪化している」
こうしたケースは、広告の目的とKPIが一致していないことが原因であることが多いです。
広告ごとに以下を必ず設定しましょう:
- この広告の目的は何か?(認知/比較/獲得)
- 測るべきKPIは何か?(リーチ/CTR/CV数など)
- そのKPIは現実的か?達成可能か?
KPIの混在は、予算の最適化ができず、評価も改善もブレる原因になります。
まとめ:ファネル設計とKPI・予算配分で広告施策は変わる
ブランド認知と獲得は、対立するものではなく、連携して成果を最大化するものです。
そのためには:
- ファネルごとに目的と役割を明確にする
- KPIを分けて評価基準を定義する
- フェーズに応じて予算配分を調整する
- 認知→興味→比較→獲得の流れを広告で設計する
広告は単発ではなく、戦略的に「流れ」を設計するもの。
一貫したファネル設計こそが、長期的な広告成果を安定させる鍵となります。
集客ならコスパ広告くんに相談がおすすめ!

※「コスパ広告くん」は弊社ボボコルンサルティング株式会社運用の、定額広告サービスです。