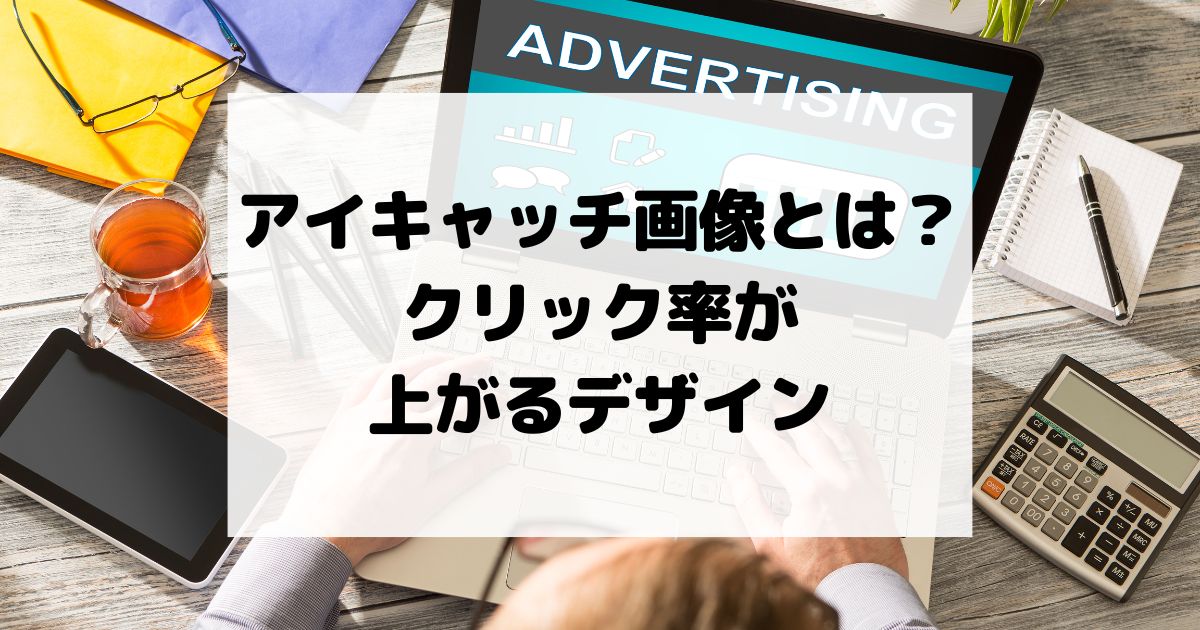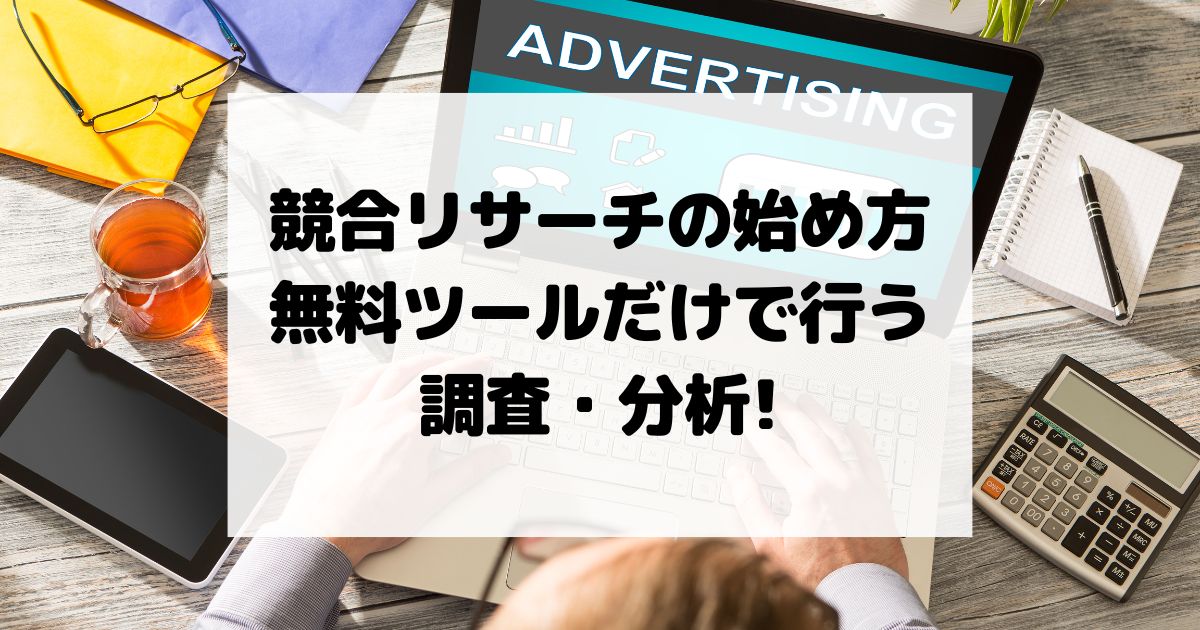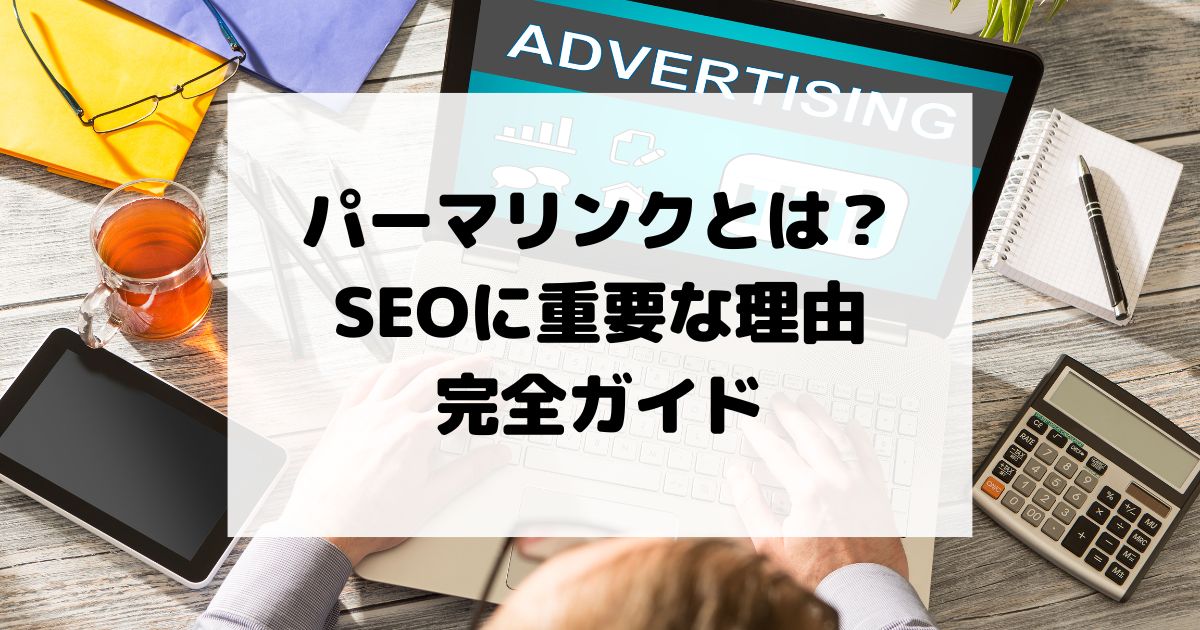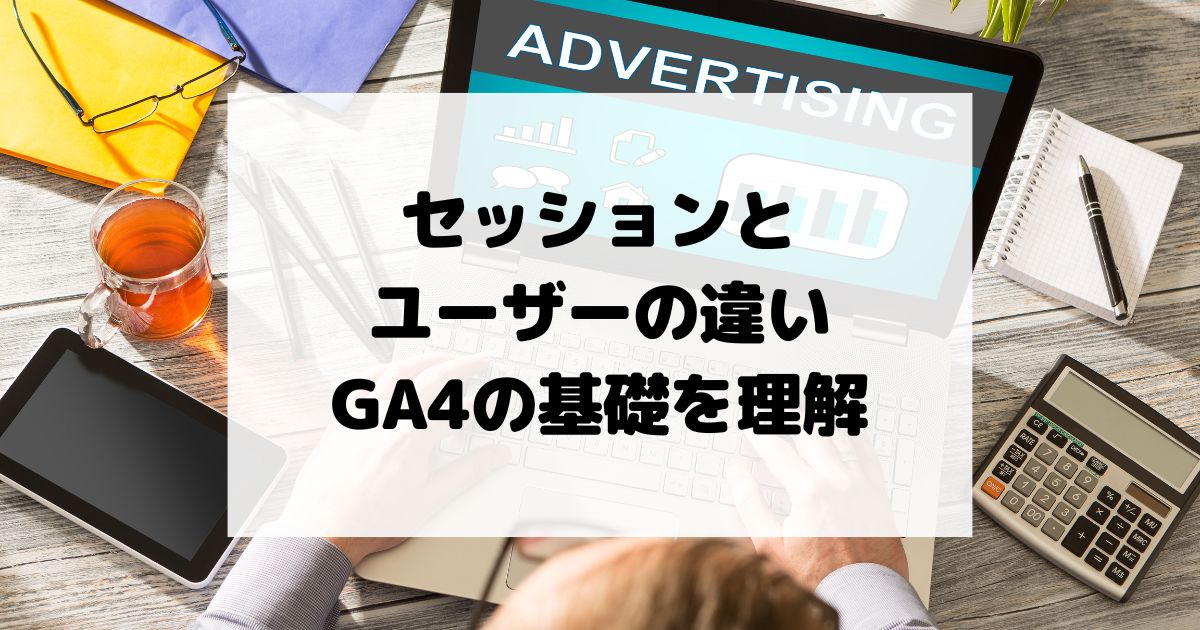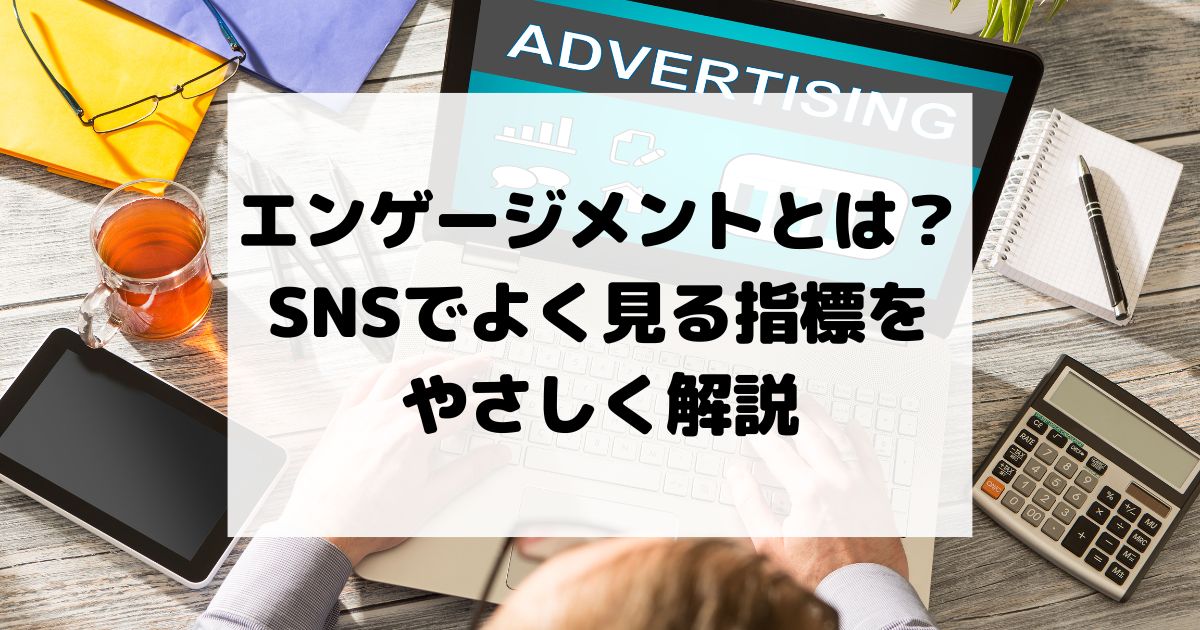直帰率と離脱率の違いをやさしく解説
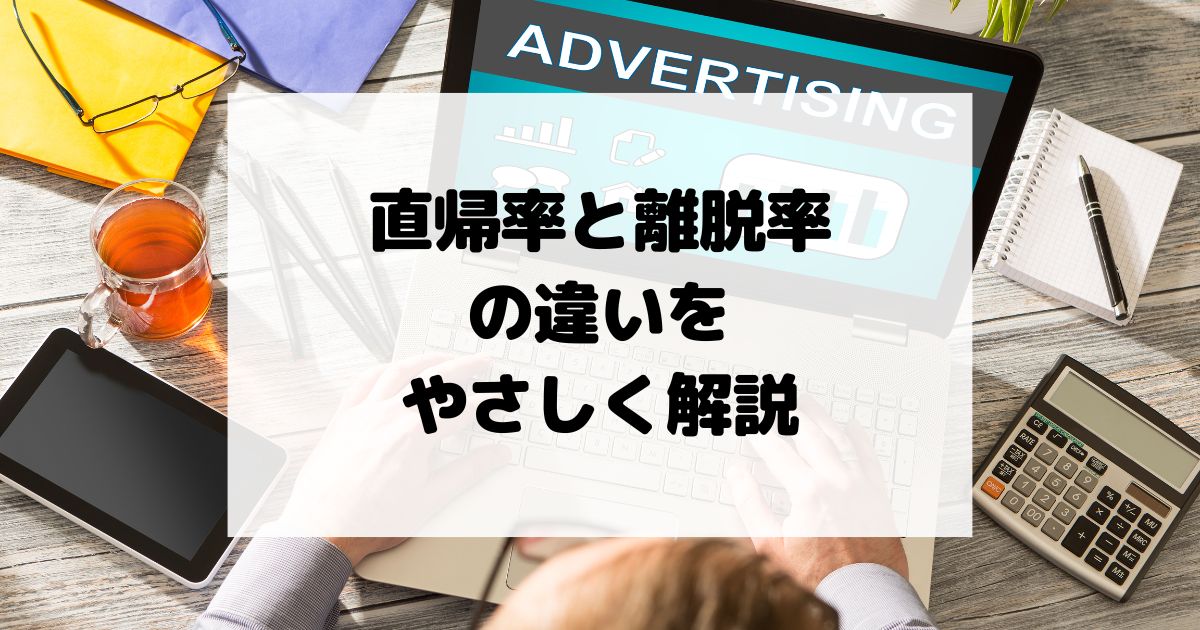
数字をただ眺めるのではなく、ユーザー行動の物語として読み解けるようになることを目指します。定義、計算の考え方、よくある勘違い、GA4での見方、改善アクション(ブログ・EC・LP別)まで実務ベースでまとめました。
用語の定義
直帰率(Bounce Rate)
- 1回の訪問で最初のページだけ見て離れたセッションの割合
- 単位はセッション。LPや集客の入口評価に使う
離脱率(Exit Rate)
- そのページがユーザーの訪問における「最後のページ」になった割合
- 単位はページ。各ページの終点になりやすさを見る
たとえば記事Aに100セッション流入し、そのうち40セッションが記事Aだけ見て離脱したなら、記事Aがランディングだったセッションに対して直帰率40%。一方、記事Aが500回表示され、そのうち100回が記事Aで訪問が終わったなら離脱率20%。
直帰率と離脱率の違いを一目で
| 指標 | 主語 | 数式イメージ | よく見る用途 | 高いときの意味 |
|---|---|---|---|---|
| 直帰率 | セッション(訪問) | 1ページだけで終了したセッション ÷ 着地セッション数 | 広告LP、集客チャネル評価 | 入口の期待不一致、読み始め前の離脱 |
| 離脱率 | ページ | そのページで終了した回数 ÷ そのページの表示回数 | 記事・商品・カート工程の評価 | そのページが終点になりやすい(良悪どちらもあり) |
注意:離脱率が高いこと自体は悪ではありません。お問い合わせ完了ページや記事の最終ページは高くて正常です。
よくある勘違い
- 離脱率が高い=悪いは誤り
完了ページ、地図・電話など出口を提供するページは離脱率が高くて正常。 - 直帰率だけでLPの良し悪しは決まらない
訪問後10秒以上の滞在やコンバージョンが起きているなら価値はある。スクロールやクリックの深度も合わせて見る。 - ページタイプを跨いで単純比較しない
トップ、記事、商品、カートでは役割が違う。役割ごとに基準線を持つ。 - デバイス差・チャネル差を無視しない
モバイル広告は直帰率が上がりがち。チャネルごとの期待値を分ける。
こんなときに何を見る?
入口の質を判定したい
- 直帰率(LPや記事の着地)+ 平均滞在、スクロール深度、ファーストビューの可視率
本文の満足度や次アクションの設計を見直したい
- 離脱率 + 次ページ遷移率、関連記事のクリック率、内部検索の利用率
売り場の取りこぼしを見つけたい
- 各工程の離脱率(商品 → カート → 配送 → 支払い)と、離脱理由(価格・送料・フォーム負荷)
GA4での見方(ユニバーサルアナリティクスとの違い)
- 直帰率
GA4ではエンゲージメント率の逆数として提供可能。直帰率 = 100% − エンゲージメント率(10秒以上の滞在、または2ページビュー以上、またはコンバージョンのいずれかを満たすとエンゲージメント扱い)。レポートに「直帰率」を追加して確認できます。 - 離脱率
GA4は「離脱率」の既定指標が薄く、ページ別の退出数/表示数から算出して見るのが実務的。探索レポートでページ(スクリーン)ごとの退出を出し、表示回数で割って離脱率相当を把握します。 - 補足
各プラットフォームのUIや指標定義は変更される可能性があります。レポート作成時はヘルプの最新定義とディメンション・指標の説明を確認してください。
典型パターンと読み解き方
パターンA:LPの直帰率が高い、CVRも低い
- 仮説:広告メッセージとLPの約束が不一致、読み込みが遅い、ファーストビューが弱い
- 追加で見る:LCP(読み込み速度)、折り返し前のCTA視認率、主要ヘッドラインのクリック
パターンB:記事の離脱率が高い、滞在は長い
- 仮説:記事で課題は解決しているが次アクションが弱い
- 施策:関連記事レコメンド、コンテンツアップセル、資料DL・メルマガのソフトCTA
パターンC:カート工程の特定ステップで離脱率が突出
- 仮説:送料の提示タイミング、会員登録の強制、入力フォームの摩擦
- 施策:送料の早期提示、ゲスト購入、フォームの自動補完・エラー文言改善
改善アクションの具体例
ブログ/メディア
- 記事冒頭の要約と目次で期待合わせ
- アイキャッチとタイトルのメッセージマッチ最適化
- 記事末に次の一歩(関連記事・カテゴリLP・資料DL)を3択で提示
LP(広告着地)
- ファーストビューに価値提案、主要CTA、信頼要素(実績・保証)を集約
- 読み込み1.5秒以内を目標に画像圧縮・フォント遅延対策
- 社会的証明(レビュー、導入社ロゴ、比較表)を折り返し前に配置
EC/商品ページ
- 価格・在庫・配送日・返品条件をファーストビューで明記
- レビューの信頼性(最新、写真付き、低評価も可視化)
- カートに追加後のクロスセルと、カート離脱者へのリマインド
フォーム/申込み
- 必須項目の削減、入力補助、リアルタイムバリデーション
- 進捗バーと保存機能で安心感を提供
- 送信後の完了ページに「次にやること」を明確に
分析の手順(再現性を高める)
- 粒度を決める(チャネル別・デバイス別・新規/リピーター別)
- 入口(直帰)と終点(離脱)を分けて、役割ごとの基準線を設定
- 正常に高いページ(完了ページなど)を除外して異常値を抽出
- 定量(率)だけでなく母数(セッション、表示回数)も並べて見る
- 仮説 → 変更点を一箇所に絞ってテスト(A/B、前後比較)
- 成果が出た型はテンプレ化して水平展開
目標設定のコツ(現実的なライン)
- 直帰率:情報記事で60〜80%、比較・取引寄りのLPで35〜55%を目安に改善余地を判断(テーマにより大きく変動)
- 離脱率:役割依存。トップやカテゴリは低いほど良い、記事末や完了は高くて正常。工程ごとに KPI を定義
数字は一般的な目安です。必ず自サイトの過去データと同種ページの中央値で比較してください。
便利な確認観点チェックリスト
- ランディング別の直帰率をチャネル×デバイスで分けて確認した
- 高直帰ページのファーストビューに価値提案・CTA・信頼要素が揃っている
- 高離脱ページが「完了系」ではないことを確認した(正常高の除外)
- カートやフォームの離脱が特定ステップに集中していないか
- 速度指標(LCP/CLS)と直帰の相関を見た
- 内部リンク設計(関連記事、パンくず、次の一歩)が機能している
- GA4の定義に沿って直帰と離脱を算出し、計測のブレを排除した
まとめ
直帰率は入口の期待一致、離脱率はページの終点としての設計を映す鏡です。役割ごとの基準線を持ち、チャネル・デバイス・ページタイプで粒度を分けて読む。定量だけでなく、スピード、ファーストビュー、導線、信頼要素という定性改善をセットで実行する。まずは上位流入のランディング10件と、CV導線上の工程ページを点検し、直帰と離脱の異常点を一つずつ潰していきましょう。
集客ならコスパ広告くんに相談がおすすめ!

※「コスパ広告くん」は弊社ボボコルンサルティング株式会社運用の、定額広告サービスです。