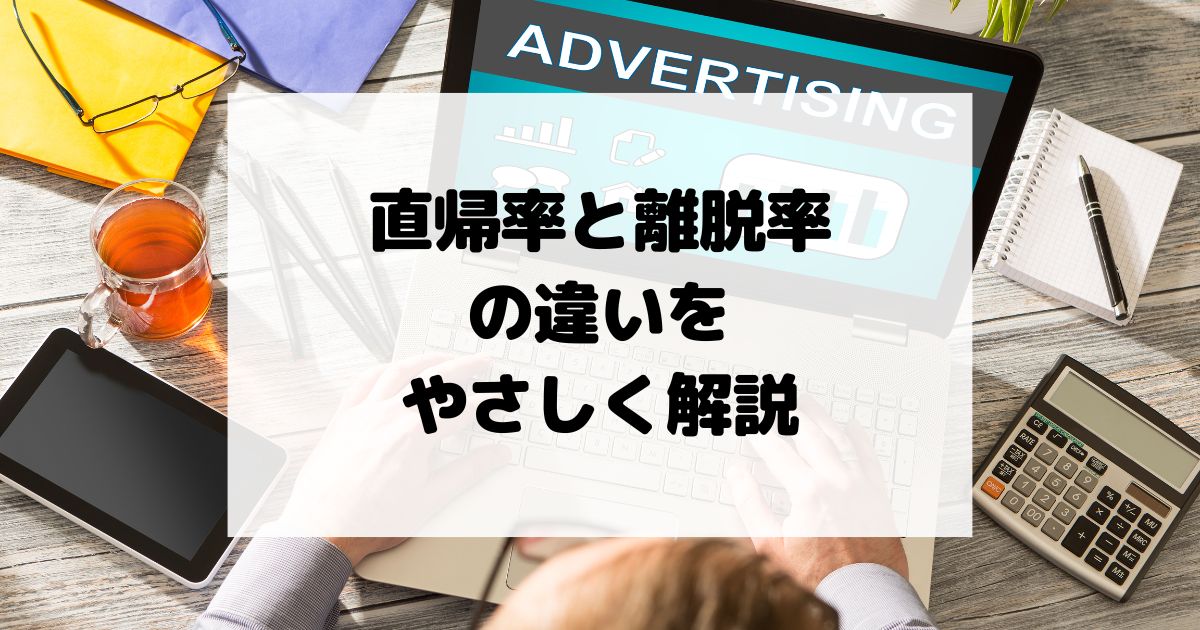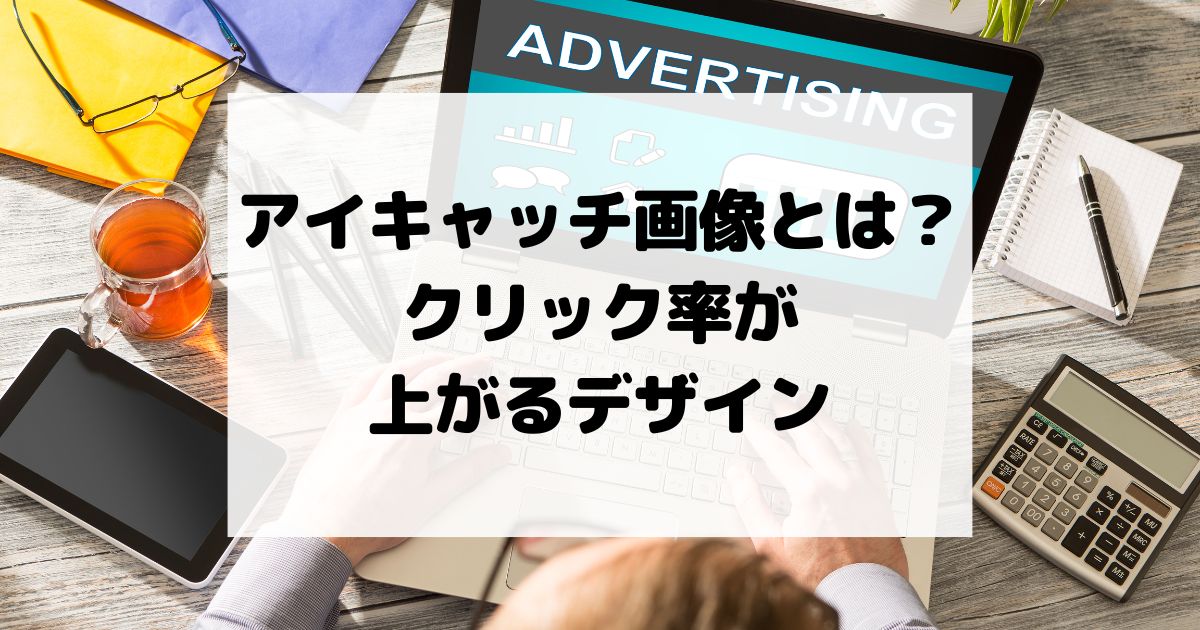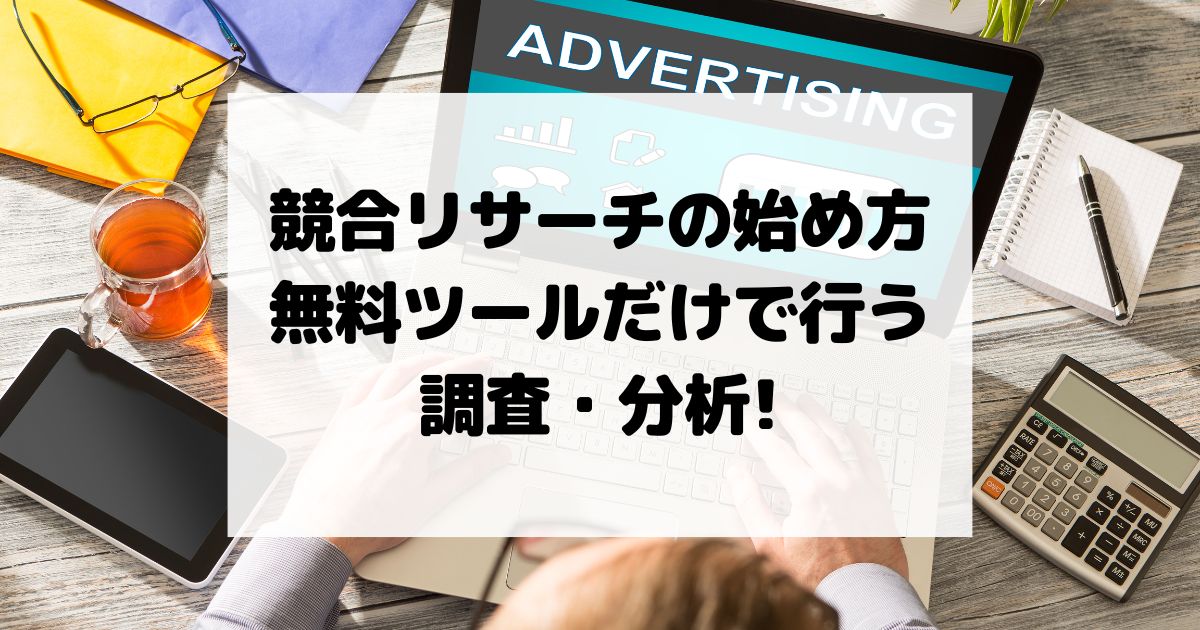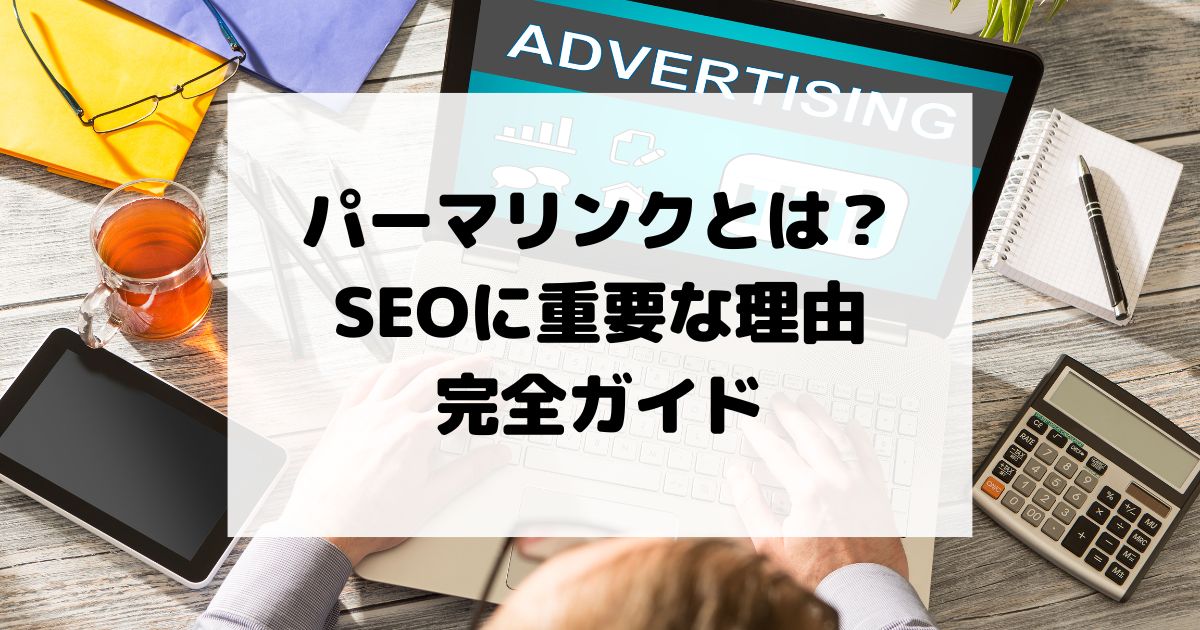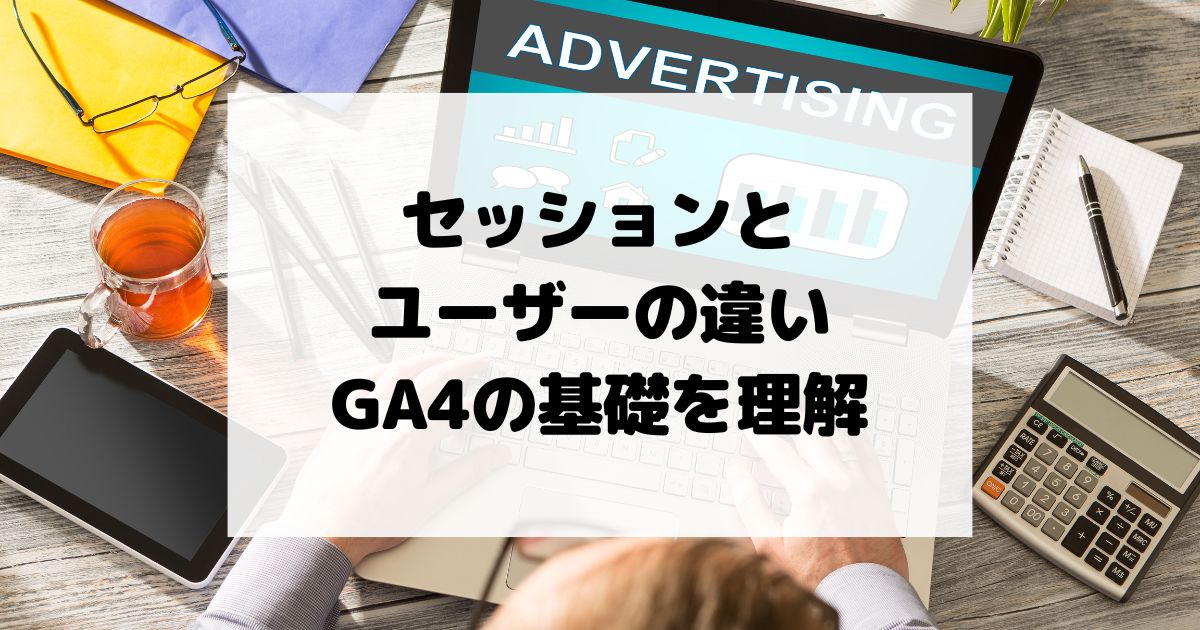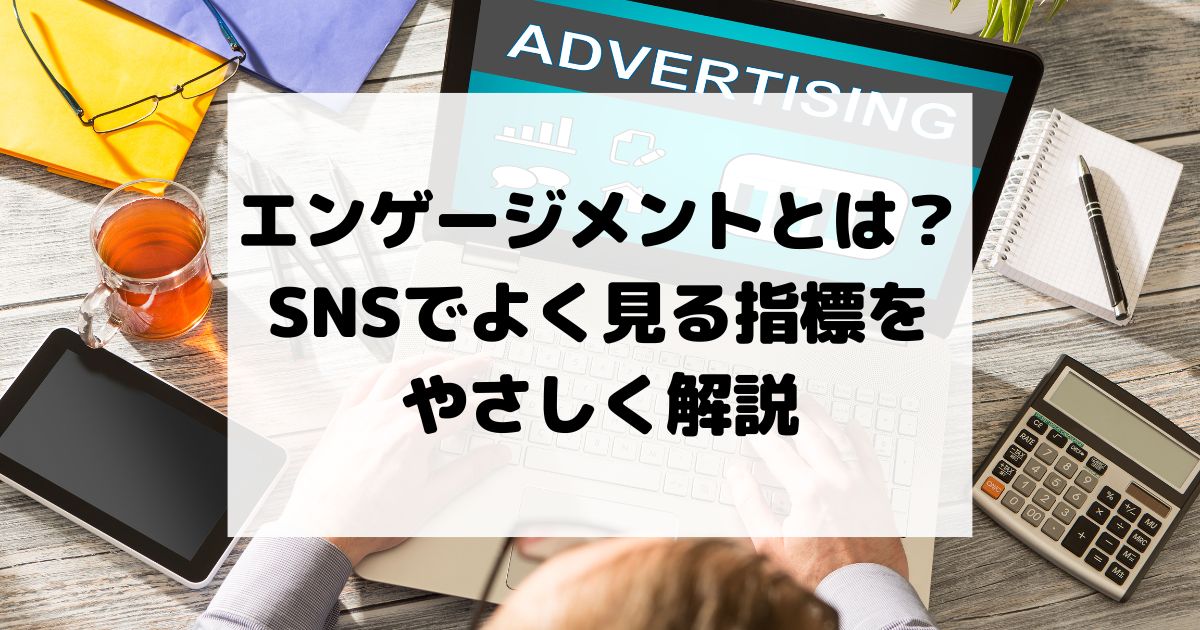WEB広告のブランドセーフティとは?企業イメージを守る運用戦略
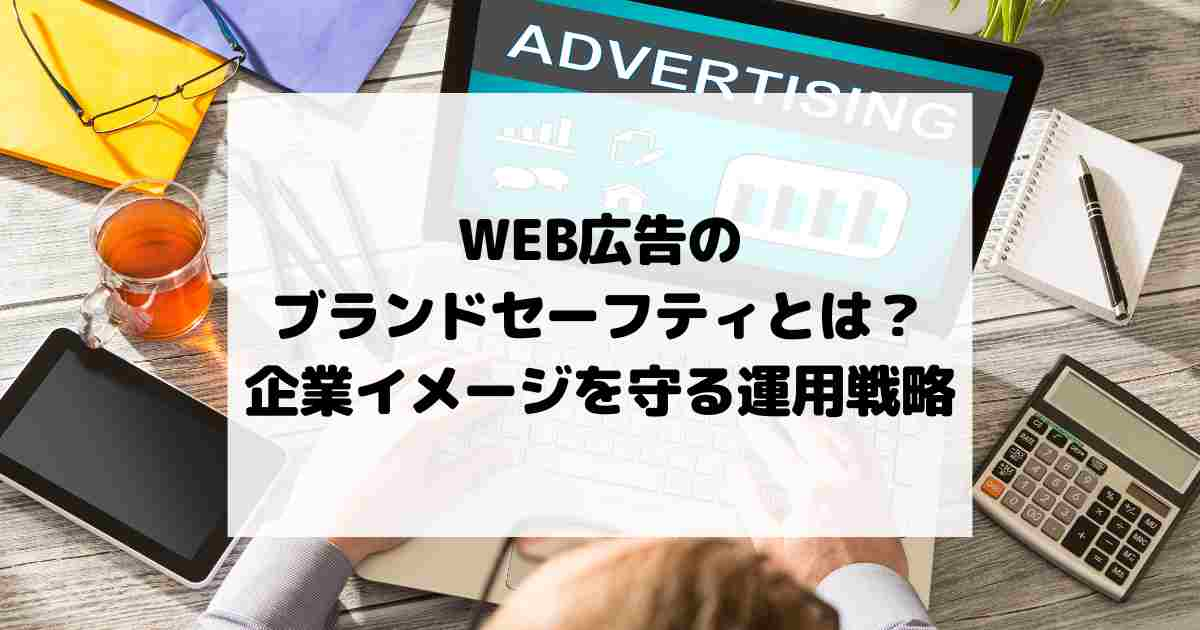
広告を配信しているのに、ブランドイメージが逆に損なわれる──そんな事態を未然に防ぐために重要なのが「ブランドセーフティ(Brand Safety)」です。今回は、Web広告運用におけるブランドセーフティの基本から、企業イメージを守るための具体的な戦略までを解説します。
ブランドセーフティとは?
ブランドセーフティとは、広告が不適切なコンテンツや望ましくない環境に表示されることを防ぎ、企業のブランドイメージを保護するための取り組みです。
たとえば、以下のようなケースはブランドイメージを大きく損ねる可能性があります。
- 暴力的、差別的、性的なコンテンツの隣に広告が表示される
- フェイクニュースや偽情報が含まれるサイトに広告が出る
- 企業のポリシーに反するコンテンツに関連付けられる
これらは、広告主が意図しない場所に広告が配信されてしまったことによる「レピュテーションリスク」です。
なぜ今、ブランドセーフティが注目されているのか?
近年、Web広告の自動配信技術が進化したことで、膨大な量の広告がリアルタイムで配信されるようになりました。特にディスプレイ広告や動画広告などは、媒体側のコンテンツと並んで表示されるため、コンテンツの質が広告の印象に直結します。
また、SNSやニュースサイトではユーザー投稿型コンテンツや偏った情報も多く、企業としてのリスクマネジメントがより重要視されるようになっています。
ブランドセーフティが脅かされる主なリスクカテゴリ
IAB(インタラクティブ広告協議会)では、以下のようなカテゴリを「ブランドセーフティのリスクが高い」と定義しています。
- ヘイトスピーチや差別的表現
- 暴力・犯罪・テロに関連する内容
- ポルノ・性的表現
- フェイクニュース・誤情報
- アルコール・ギャンブル
- 政治的・宗教的にセンシティブな話題
これらのコンテンツと広告が隣接して表示されると、ユーザーに「この企業はこういうメディアを支持しているのか」という誤解を与える可能性があります。
ブランドセーフティを実現するための戦略
1. 配信先の精査と除外設定
Google広告やMeta広告(Facebook/Instagram)では、配信先のドメインやコンテンツカテゴリを除外する設定が可能です。
- Googleディスプレイ広告では「コンテンツ除外カテゴリ」や「プレースメント除外」が有効
- Meta広告では「ブロックリスト」を活用し、特定のサイトやアプリを事前に除外
2. コンテキストターゲティングの活用
従来のユーザーターゲティングに加え、掲載面の文脈(コンテキスト)を分析して広告を配信する手法です。たとえば、「健康」に関するコンテンツ内に健康食品の広告を出すなど、ブランドとの親和性を重視した配信が可能です。
3. ホワイトリストの運用
信頼できるメディアや配信先だけをリスト化し、そのリスト内に限定して広告を配信する方法です。ブランドセーフティを強化したい場合は、ホワイトリスト方式で配信先を絞り込むのが有効です。
まとめ:成果だけでなく“守る広告運用”を意識しよう
Web広告は成果を追求するだけでなく、企業の信用やブランド価値を守るという側面も持っています。いかに効果が高い広告でも、表示される場所によっては企業にとって大きなマイナスになることがあります。
ブランドセーフティは「後回し」ではなく、広告戦略の初期段階から組み込むべき必須の視点です。成果と信頼の両立を実現するために、ぜひ広告運用の中にブランドセーフティの考え方を取り入れてみてください。
集客ならコスパ広告くんに相談がおすすめ!

※「コスパ広告くん」は弊社ボボコルンサルティング株式会社運用の、定額広告サービスです。